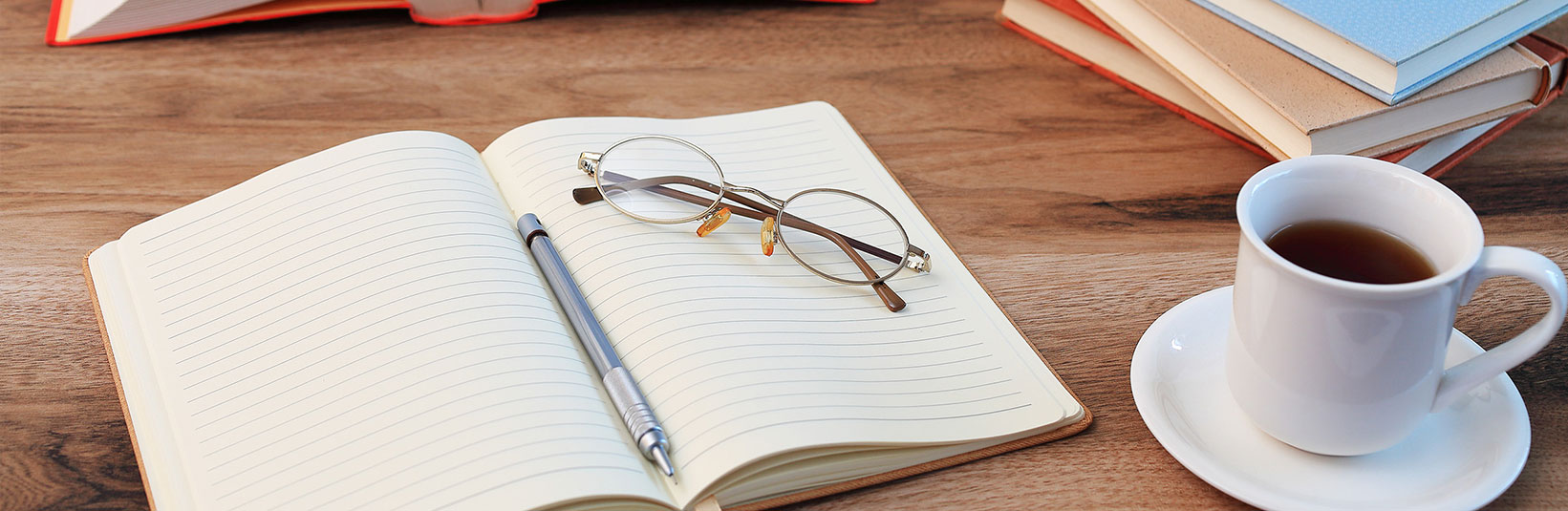
大切なご家族や、身近な人に介護が必要になったとき、どうすればよいのか?どこに相談すればよいのか?
介護サービスの種類やサポートサービスの利用方法などを、分かりやすく紹介します。

-
支える心得
-
介護は突然やってくる!?
まだ元気だから大丈夫と安心していませんか?突然、思いもよらない病気や事故に見舞われたり、階段の上り下りが大変になる、記憶力が低下するなど、日常生活に不自由が生じてくると誰かの手助けが必要になります。
いざ介護が必要になった時に戸惑うことがないよう、日頃から備えておくことが大切です。要介護状態になる原因とは?

介護が必要となる原因は人それぞれですが、厚生労働省が発表した統計データによると、
1 認知症 16.6% 2 脳血管疾患(脳卒中) 16.1% 3 骨折・転倒 13.9% 4 高齢による衰弱 13.2% 5 関節疾患 10.2% 出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和4年)
これらが上位5位となっています。
こうした原因によって食事、入浴、排泄、移動といった日常生活に困難が生じた時、 利用できるのが介護サービスです。
-
家族に介護が必要になる前に準備しておきたいこと
いざ介護が必要になった時に的確な支援を受けるためには、介護状態になるまでの経緯や生活習慣を把握しておくことが望まれます。ご両親や家族とコミュニケーションをとり、毎日どのように過ごしているのか様子をみましょう。
「朝は何時に起きているのか」「食事は3食摂っているのか」「入浴や就寝時間は」などの生活リズムや交友関係などの情報があると、介護体制をスムーズに整えることができます。
次に、医療・健康面の情報も大切です。「どこに通院しているのか」「持病の状況は」などの情報は必要不可欠。お薬手帳などを確認してご両親や家族の病歴(既往歴)や飲んでいる薬、かかりつけ医などを把握しておくと安心です。
また、もの忘れや記憶力の低下、自宅の住環境(段差などの危険箇所の有無)の確認も忘れずに行いましょう。
-
介護が必要になった時
●要介護者の心身の状態(障害やマヒの有無、日常生活での不便など)や住まいの状況、家族の要望など必要な情報を整理しましょう。
●家族で介護のプロジェクトチームをつくり、キーパーソンを決め、今後必要な準備やそれぞれの役割分担 (食事・買い物のサポート、通院の送迎、費用負担など)について確認します。
●地域包括支援センターや市区町村の窓口が相談に応じてくれます。まずは相談してみましょう。
◎慌てず悩まず、まずは相談
介護をサポートしてくれる制度として、介護保険制度があります。利用するためには“要介護認定の申請”が必要です。
まずは、お住まいの市区町村にある介護保険の窓口や介護認定申請の代行も行っている「地域包括支援センター」に相談しましょう。
-
-
介護保険制度
-
介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、介護の必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人に加入義務があり、市区町村が運営しています。
日常生活に介護や支援が必要と認定されたときには、心身の状況に応じた介護サービスを利用料の1~3割負担で受けることができます。◎介護保険サービスを利用できる人
- ●65歳以上の人(第1 号被保険者)で、介護が必要と認定された場合
- ●40~64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)で、国の定めた16特定疾病により介護が必要と認定された場合
16疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 - 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または
股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
-
介護保険サービスの利用方法
介護保険のサービスを利用するには、市区町村の窓口へ【要介護認定】の申請をする必要があります。申請すると市区町村の依頼により“かかりつけ医”が主治医意見書を作成します。また、訪問調査員が利用者宅や入院先等を訪ね、本人や家族と面談し介護が必要なレベルを調査します。
認定結果は、【要支援1】から【要介護5】まで7段階あり、レベルごとに介護保険の支給限度額と受けられるサービスが決まっています。介護保険サービス利用の流れ

申 請
本人や家族または代理人が市区町村の窓口に「要介護認定」を申請する。

認定調査
調査員が利用者宅や入院先を訪れ、介護状況について質問し調査票を作成する。

要介護認定
認定調査会による判定が行われる。コンピュータによる1次判定の結果に、調査員の特記事項や主治医の意見書を合わせて2次判定され、要介護度が決定する。

認定結果の通知
申請から原則30日以内に通知が届く。

ケアプランの作成
要支援1・2│地域包括支援センター・ケアマネジャーに依頼する。
要介護1~5│ケアマネジャーに依頼する。
サービスの開始
契約、利用開始。
◎要介護度と給付金額の目安
訪問・通所・短期入所・福祉用具貸与などの各種介護サービスを利用する際の支給上限額をご紹介します。
要支援 1│月額 50,320 円
自己負担額 ●1割/ 5,032 円
●2割/ 10,064 円
●3割/ 15,096 円要支援 2│月額 105,310 円
自己負担額 ●1割/ 10,531 円
●2割/ 21,062 円
●3割/ 31,593 円
生活機能が改善する可能性が高い人。介護は必要としないが、洗濯や買い物など日常生活での支援が必要。
要介護 1│月額 167,650 円
自己負担額 ●1割/ 16,765 円
●2割/ 33,530 円
●3割/ 50,295 円歩いたり、座ったりできるが、外出時のつきそいや、入浴などに一部介助が必要。

要介護 2│月額 197,050 円
自己負担額 ●1割/ 19,705 円
●2割/ 39,410 円
●3割/ 59,115 円歩いたり、座ったりが不安定で、トイレ、入浴、衣服の脱ぎ着などに一部または全介助が必要。また、もの忘れにより生活に支障をきたす場合などがある。

要介護 3│月額 270,480 円
自己負担額 ●1割/ 27,048 円
●2割/ 54,096 円
●3割/ 81,144 円歩く、座るが自力でできず、トイレ、入浴、衣服の脱ぎ着、食事などに一部または全介助が必要。また、徘徊などの問題行動が見られる場合がある。

要介護 4│月額 309,380 円
自己負担額 ●1割/ 30,938 円
●2割/ 61,876 円
●3割/ 92,814 円トイレ、入浴、衣服の脱ぎ着などに全面的介助が必要。本人との意思の疎通ができないこともある。

要介護 5│月額 362,170 円
自己負担額 ●1割/ 36,217 円
●2割/ 72,434 円
●3割/ 108,651 円寝たきりで、日常生活全般に全面的介助が必要。本人との意思の疎通ができないこともある。

-
認定調査のポイント
要介護認定とは、利用者が介護保険制度で“どの程度の介護が必要か”を公的に認定するものです。
認定調査では能力や介護の方法など74の項目にそって調査員が話を伺います。訪問調査を受ける際には、利用者のありのままの状態を調査員に見てもらう必要があります。
利用者が見栄や羞恥心から普段よりも元気に振舞ってしまうと正確な判断を妨げ、実際の介護度より軽く認定される可能性もあります。特に認知症の方の場合は、注意が必要です。
◎訪問調査の質問事項例
歩 行 ●立った状態から5メートル程度歩けるか
●手すりなどにつかまれば歩けるか
●介助が必要か
●外出の頻度はどれくらいか など
排 泄 ●排尿、排便が一人でできるか
●衣類の着脱や後始末の介助が必要か など
寝 返 り ●寝返りができるか
●一人でできるか
●何かにつかまればできるか
●介助が必要か など
起き上がり ●寝た状態から上半身を起こすことができるか
●一人でできるか
●ベッドの手すりなどにつかまればできるか
●介助が必要か など
食 事 ●一人で食事をとることができるか
●むせたりしないか
●誰かの助けを必要とするか など
立ち上がり ●椅子、ベッド、車いすなどから
立ち上がることができるか●何かにつかまればできるか
●介助が必要か など
視 力 ●「見えるか」「見えないか」 それがどの程度か
●新聞や雑誌また調査員が持参した絵などで
視力を確認 など認知に関して ●自分の名前が言えるか
●今の季節がわかるか
●物を盗まれたなどの被害妄想はあるか など
訪問調査を受ける日の心構え
- ●普段、介護している方が同席して、毎日の生活の様子を伝えましょう
- ●リラックスして、なるべく普段どおりの生活を見てもらうように心がけましょう
- ●できること、できないことを正直に伝えましょう
- ●「失禁する」とか「もの忘れがひどい」など、本人の前で言いにくいことは、本人のいない場で調査員に伝えましょう
- ●認知症などの場合、その日によって状態が変化することがあるので、日頃の生活状況をメモしたものを用意しておきましょう
-
自分らしく生活するための在宅サービス
介護が必要になっても自分らしく生活するためのサポートとして在宅サービスがあります。介護される人が快適に過ごすことができ、介護する家族の負担も軽減できるサービスを紹介します。
-
訪問サービス
◎訪問介護 (ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、掃除や買い物などの生活援助や排泄、入浴などの身体介護を行う。
◎訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、血圧測定や健康チェック、療養上の世話などを行う。
◎訪問入浴介護
自宅に専用の浴槽を持ち込み、介護スタッフや看護師が入浴を介助する。
◎訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などの専門職が自宅を訪問し、リハビリを行う。
◎居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、相談や助言を行う。
-
通所サービス
◎通所介護 (デイサービス)
デイサービスセンターなどに日帰りで通い、レクリエーションや食事、入浴などのサービスを受ける。
◎通所リハビリテーション (デイケア)
介護老人保健施設や医療施設に日帰りで通い、リハビリや食事、入浴などのサービスを受ける。
-
短期入所サービス
◎短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに泊り、食事や入浴などのサービスを受ける。介護する家族の休養のためにも利用できる。
◎短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護医療院などに泊り、機能訓練や食事などのサービスを受ける。介護する家族の休養のためにも利用できる。
-
地域密着型サービス
◎小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、訪問や泊まりのサービスを組み合わせて受ける。
◎認知症対応型通所介護
認知症高齢者がデイサービスに日帰りで通い、専門的なケアを受ける。
◎認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が少人数で共同生活を送りながら生活支援や介護サービスを受ける。
◎夜間対応型訪問介護
夜間に自宅を訪問したホームヘルパーから安否確認や身体介護を受ける。
◎地域密着型通所介護
利用者数が18人以下の小規模デイサービスに日帰りで通い、レクリエーションや食事、入浴などのサービスを受ける。
◎地域密着型療養通所介護
利用者数が18人以下の小規模デイサービスに日帰りで通い、機能訓練や医療などのサービスを受ける。
◎地域密着型特定施設入居者生活介護
利用者数30人未満の小規模な有料老人ホームで生活支援や介護サービスを受ける。
◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
利用者数30人未満の小規模な特別養護老人ホームで生活支援や介護サービスを受ける。
◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護
巡回や通報システムにより介護・看護サービスを24時間必要なタイミングで受ける。
◎看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを受ける。
-
福祉用具・住宅改修
◎福祉用具の貸与
車いすや電動ベッドなどの福祉用具のレンタルサービス
※要支援1~要介護1に認定された方は、一部対象とならない用具があります。◎福祉用具購入費の支給
寝室などに置いて排泄ができるように持ち運びが可能なトイレ(ポータブルトイレ)や浴室で立ち座りし易い安定性の高い浴室用のいす(シャワーチェア)など、排泄や入浴の際に利用できる福祉用具の購入費の一部を支給します。
◎住宅改修費の支給
手すりの取付け、段差の解消などの住宅改修を行った際の費用の一部を支給。
生活支援サービス(介護保険以外のサービス)

介護保険の枠にとらわれない、地方自治体や民間企業、NPO法人、ボランティアなどによる在宅介護生活支援サービスです。地域の実情に即し、介護する人・される人のニーズに細やかに応えてくれます。
●家事援助サービス ●配食サービス ●移送サービス
●訪問理美容サービス ●寝具乾燥サービス ●緊急通報サービス
●見守りサービス ●トラベルサポートサービス
●位置情報サービス などその他のサービス

地域支援事業 (介護予防事業)
地域包括センターのもと、介護保険非該当の方を対象にした転倒予防教室や口腔ケア、栄養指導などを行います。
法定後見制度
判断能力が低下した高齢者の財産管理や生活支援をサポートする制度です。
障害者総合支援法
身体・知的・精神障害の方でケアが必要な場合、市区町村への申請により必要なサービスが利用できます。
-
-
ケアマネジャーとは
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、医療・福祉の国家資格を有する介護の専門家です。家族とサービス事業者をつなぐキーパーソンの役割を担っています。
ケアマネジャーの主な仕事
●介護生活をトータルにサポート
●ケアプランの作成
●専門職チームのコーディネーター役
●サービスの管理と評価ケアマネジャー選びのポイント

ケアマネジャーは、利用者の生活を左右する重要な存在。要介護の認定を受けた場合は、ケアマネジャーは利用者が自分で選択します。要支援の場合は、住所地の地域包括支援センターまたはケアマネジャーが担当します。
要介護認定を受けた際にもらう「居宅介護支援事業者」一覧などから選ぶことになりますが、ケアマネジャーは保有資格によって得意分野があるので、実際に電話などで連絡をした際に持っている資格や経歴などを聞いてみてもよいでしょう。
また、決める前に実際に会って話をして、人柄や相性などを確かめることも重要です。利用者だけでなく家族の立場などもあわせて、より良い介護生活を考えてくれるケアマネジャーに出会うために、「地域包括支援センター」に相談するのもよいでしょう。
-
-
介護保険と制度の活用
-
介護保険サービスの活用例(ケアプラン事例と費用)
ケアプランは、利用者の心身の状況、生活環境、家族の希望などを考慮して、必要な介護サービスを選択し組み合わせるので、一人ひとり異なります。
◎ケアプラン例(要介護3)
介護保険・月額利用限度額/270,480円
40代のAさんが車いすのお父様(78歳)を自宅で介護する場合- ●3ヶ月前、同居するお父様が脳梗塞を発症、左半身に麻痺が残る。
- ●リハビリの結果、自分で車いすを操作して短い距離なら移動できるように。
- ●利き腕は使えるが、着替えや入浴などに介助が必要な状態。
- ●お父様の希望もあり、介護保険制度を活用しながら、自宅で介護。
-
仕事と介護の両立のために
近年、家族の介護を理由に仕事を辞める方が増えています。働く世代にも影響を与えることから、サポートするための制度も少しずつ増えてきました。国としても「介護休業制度」を設け、働く人々をサポートしています。
会社によってサポート内容は異なりますので、まずは人事部などの担当部署に相談してみましょう。
-
公的な制度を上手に活用! 医療費・介護費の負担を軽減しよう
高齢になると、病院や歯科へ通院する機会が増えてきます。大きな病気や怪我がなくとも、定期的に受診・服薬する方もいるでしょう。一般的に70歳以上の方が医療機関の窓口で支払う医療費はかかった費用の1割ですが、長期にわたる入院や高額な治療を行なった場合などにはその費用がふくらみ、限りある収入の中で家計を圧迫する心配もあります。
そのような経済的負担を軽くするため、公的な医療保険・介護保険には、支払った自己負担額が一定金額を超えた場合、差額分が払い戻される「高額医療費」制度が設けられています。
また、税金面でも、医療費が一定額を超えると所得税・住民税が軽減される「医療費控除」制度があります。-
高額医療費制度
被保険者や被扶養者の方が、1カ月(月初から月末まで)の間に医療機関の窓口で支払った保険診療の対象となる医療費(一般的な治療や入院費)が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その差額が払い戻される制度です。払い戻しを受けるには、原則被保険者からの「申請」が必要です。
70歳未満の方は医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いで済み、高額な医療費を立て替える必要がなくなります。「限度額適用認定証」の発行は加入している医療保険の窓口へお申し込みください。
70歳以上の方は特に手続きの必要はなく、自動的に自己負担限度額までの支払いとなります。
-
高額介護サービス費制度
「要介護」「要支援」の両方の方が利用できます。ひとつの世帯で、1カ月(月初から月末まで)の間に介護保険の介護サービスを利用して支払った金額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分の金額が払い戻される制度です。
介護保険による在宅サービスおよび施設サービスを利用して支払った1割の自己負担額が対象。福祉用具購入および住宅改修費の自己負担分、入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費 などは高額介護サービス費の対象となりません。
市区町村から支給該当対象者に郵送される「高額介護サービス費支給申請書」を介護保険の窓口に提出します。この申請は一度行なっていただければ、次回以降は自動的に登録した口座に振り込まれます。
自己負担限度額は、その方の所得によって細かく設定されています。ご自分の限度額を確認する場合は、医療保険の窓口にお問い合わせください。
-
高額介護合算療養費制度
ひとつの世帯で、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している方が、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)の間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その差額が払い戻される制度です。
保険給付の対象となる医療費・介護費のみです。入院時の差額ベッド代や食事代、自由診療など保険外の診療は対象外となります。
払い戻しを受けるには、世帯主からの「申請」が必要です。介護保険の窓口に「介護自己負担額証明書」の交付を申込み、その証明書を添付して加入している医療保険の窓口に申請します。その後、医療保険・介護保険それぞれから支給額が支払われます。支給の申請は翌年8月1日からできます。●高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日まで1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額です。
●自己負担限度額は、その方の年齢や所得によって細かく設定されています。ご自分の限度額を確認する場合は、加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
-
医療費控除制度
「生計を一つにする」ひとつの世帯で、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)の間に医療費の支払いが10万円以上あった場合、確定申告により払いすぎた税金が還付される制度です。
医療費だけでなく、介護保険の居宅サービスや施設サービスを利用して支払った介護費用の一部、おむつ代(おむつ使用証明書要)や交通費なども控除の対象となります。控除の対象となる医療費・介護費については国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
所定の資料を添付した確定申告書を住所地のある税務署に提出して行ないます。インターネットや郵送でも手続きすることができます。確定申告の申請期間は毎年2月16日~3月15日です。(期日が土日と重なる場合はこの限りではありません)●申告の際には支払を証明する領収証や医療費の明細書を添付する必要があります。日頃から保管しておくようにしましょう。
●申告にあたり、払い戻された「高額療養費」や「高額介護サービス費」などは医療費から差し引いて計算します。
-
-
注目される民間の介護保険。万が一の介護に+αの備え
病気や介護のためにかかった費用が高額となっても、「高額療養費制度」や「高額介護サービス費」などを利用することで、自己負担額は一定額に抑えることができます。
しかし、公的な保険だけではカバーできない入院時の差額ベッド代や食事代、介護保険の利用限度額を超えたサービスなどの自費部分も少なくないのが現実。介護が必要になった時の自己負担額を軽くする方法として、民間の介護保険が注目を集めています。
商品の特徴や公的な保険との違いなど民間の介護保険の基礎知識を紹介しましょう。◎民間の介護保険
保険会社が定める要介護状態になったときに介護一時金や介護年金が支払われる、公的介護保険を補完する位置づけの保険です。生命保険会社、損害保険会社、共済等が販売しており、保障内容も商品により多種多様です。
公的な保険と違い、40歳未満でも加入でき給付も受けられます。現金での給付が受けられ、用途も自由。保険によっては貯蓄性も望めるなどのメリットがある一方、新たに保険料の支出が増えるという負担も。保険金の支払い条件や預貯金とのバランスを考慮して、ご自分のニーズにあった商品を選択する必要があります。保障以外にも、契約者やその家族向けに介護・健康に関する電話相談や介護セミナーの開催、介護施設情報の提供など介護関連のサービスを充実させている保険会社が増えてきました。ご自分のニーズに合わせて是非活用したいものです。
-



